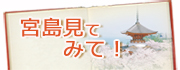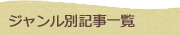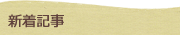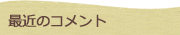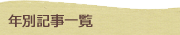11月3日。
宮島は観光客で人が多かったです。
ひときわにぎやかだったのが「大願寺」
火渡り式(厳島大仏不動明王柴灯護摩祈願法要)が、
とりおこなわれていました。
なんの知識もないままに見物。
太く響くいい声でなにやら唱えていて、迫力があります。

火がつけられると煙がもくもく。
煙の行く方に陣取っている人が後ろに下がっていくほどです。

火が消えてきたかなと思っていたら、
しゃもじが投げ入れられてまた火が大きくなったり。

ホラ貝も場を盛り上げます。
みんな顔が赤くなって熱そうでした。
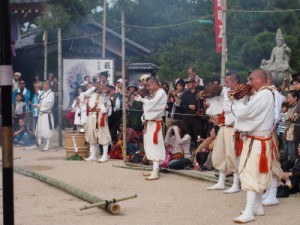
竹で叩いたりして、火の色が見えなくなり、
渡れそうな雰囲気に。


お箸のような細い炭が投げ入れ、
足場が整えられたふうになったのはいいのですが、
また火が勢いを取り戻してしまいました。
「いい感じに消えていたのに」
私と同じようにはじめて見る人も多いらしく、
どのタイミングでだれが火を渡るのか話しています。
「ああ、また危ない感じになった」という火の強さのとき、

数人が縦に並び、一気に火を渡りました。
歓声があがります。


「これから走りますよって相図してくれればいいのに」と、後ろから声。
私もそう思いました。
「太鼓の音で走る瞬間がわかった。しっかり撮れた」
という人もいましたが、私はわかりませんでした。

そして、再び火は鎮火へ向かい、
塩が袋からバサッとまかれました。
「あっ業務用」と声。…茶色い紙袋に食塩の青文字が。
次は一般の人が渡ります。
しっかりと火は消されたまま。

一般の人たちが列を作って火を渡る順番を待っているのを
向かいの宝物館から撮りました。↓ ↓

今日はなるべく人の少ないところへ行こうと思っていたのに、
やはり人が集まっていると気になってしまい、
火渡り見物に時間を費やしました。
いいものを見せてもらいました。







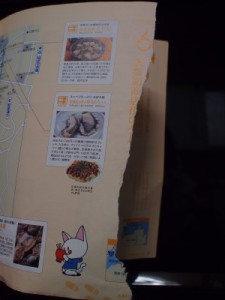






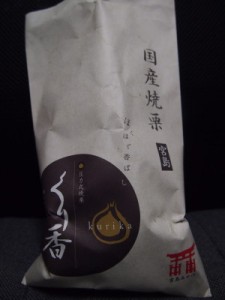







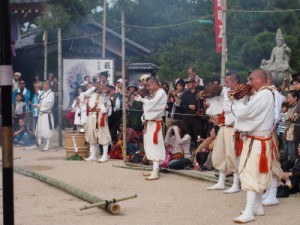











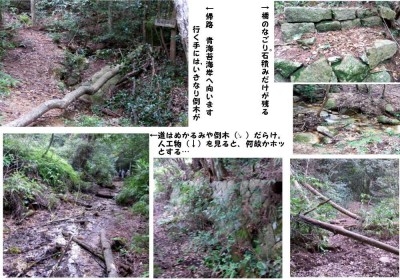
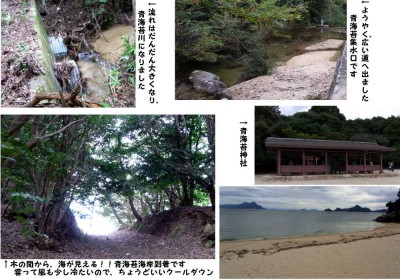
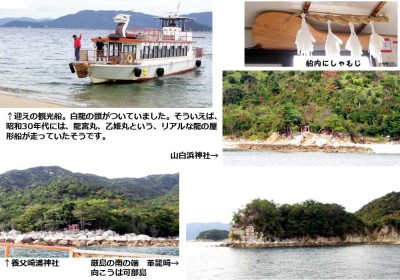
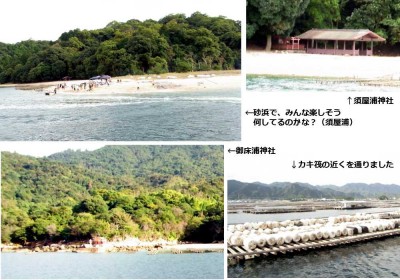
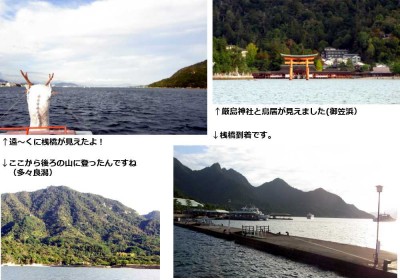

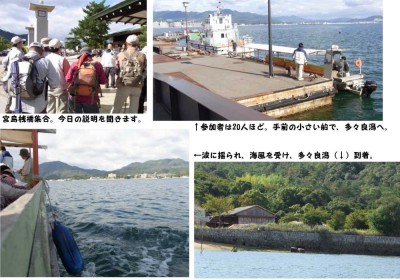
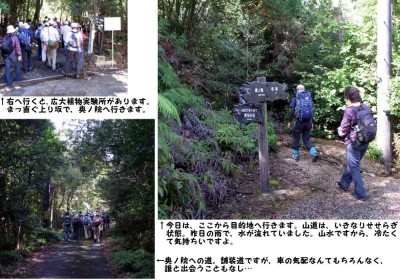
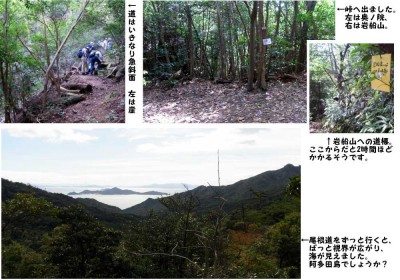




 (*^_^*)ここは大願寺前
(*^_^*)ここは大願寺前